こんにちは、るるやまです。この記事は私が大切にしている『ビジネス小説』の原点。最近公開した「実用書10選」とあわせて読むと、知識が面白いほど繋がりますよ!
診断士として活動して20年。多くの経営者や現場と向き合う中で、痛感していることがあります。それは、「優れたビジネス理論は、血の通った物語(ストーリー)として理解してこそ、本当の武器になる」ということです。
私は最近、診断士の知見に加え、FP(お金)と宅建(不動産)という「人生の三種の神器」を半年で手に入れました。その学びの根底にあるのは、常にこうしたビジネス小説から得た「現場のリアル」や「経営の本質」です。
今回は、私が20年のキャリアの中で何度も読み返し、戦略思考やマネジメントの血肉としてきた10冊を厳選してご紹介します。
1.「経営戦略」をテーマとした本2冊の紹介
2.「マーケティング」をテーマとした本2冊の紹介
3.「財務・会計」をテーマとした本2冊の紹介
4.「組織」をテーマとした本2冊の紹介
5.「生産管理(TOC」」をテーマとした本2冊の紹介
1.「経営戦略」をテーマとした本2冊
経営戦略は、会社の方向性を決定する重要な方針ですが、大企業ですと経営企画というような社長直轄の部署が、経営戦略を担当することが多いですね。ご紹介する本2冊は、会社の経営がうまくいかない時に、どのような全社戦略を取るかを、組織のトップや経営企画、という視点・役割から企業変革を行っていくストーリーの小説です。
(1)「V字回復の経営〜2年で会社を変えられますか 企業変革ドラマ〜」
診断士として20年経った今読み返しても、組織変革の生々しさに背筋が伸びます。FPや宅建の視点を加味しても、やはり『現場の数字』が動く瞬間の描写は普遍的です。この他にも4部作として、下記3冊のビジネス小説を出版されてますが、どの小説も非常に読みやすく白身のストーリーで一気読みできますし、経営戦略への理解度が高まります。
2.企業の変革に必要な方法
3.経営者人材を育成し組織を改善するための方法
株式会社ミスミグループ本社シニアチェアマン 第2期創業者
20代をボストン・コンサルティング・グループの国内採用第1号コンサルタントとして活躍した後、30代以降経営者や事業再生のプロとして活躍し、2002年からミスミグループ本社のCEOに就任し、同社を10年間で従業員340人の商社から7000人を超えるグローバル企業へ変革したプロ経営者
(2)「戦略参謀〜経営プロフェッショナルの教科書」
経営トップ参謀として「経営企画」という機能があります。その機能に初めて着任した主人公を通して、事業のP(計画)D(実行)C(確認)A(改善)のサイクルを効果的に回す仕組みの構築方法を学ぶ事ができる小説です。
途中の章ごとに著者の解説があるので、ストーリーを楽しみながら、理論的な背景なども学ぶ事が可能になっています。
2.企業変革の進め方とは
3.事業のPDCAのサイクルの効果的な回し方とは
株式会社RE‐Engineering Partners代表で経営コンサルタント。
豊田自動織機製作所よりの企業派遣で米国コロンビア大学大学院コンピューターサイエンス科にて修士号を取得した後、マッキンゼーアンドカンパニーに入社。マッキンゼー時代は、大手電気企業、大手建設業、大手流通企業などの戦略策定や経営改革などに携わる。その後は、企業側の依頼により、大手企業の代表取締役社長、役員、事業・営業責任者として売上V字回復、収益性強化などの企業改革を行う。
2.「マーケティング」をテーマとした本2冊
アメリカ・マーケティング協会は、「マーケティングとは、消費者、顧客、パートナー、および社会全体にとって価値のある提供物を創造、伝達、流通、交換するための活動、一連の精度、およびプロセスをいう」と定義しています。
下記2冊では、顧客が求める商品やサービスを開発し、その情報を発信し、その価値を効果的に得る事を可能とする一連のプロセス(活動)について理解をする事ができます。
(1)「100円のコーラを1000円で売る方法」
「そんな事が可能なのかな?」というキャッチなタイトルの本ですが、破天荒な女性の商品開発プランナーが上司から指導を受けながら商品開発からマーケット投入までのプロセスの中で成長していく物語で読むと納得できます。
バリュープロポジションという「競合他社が提供できる価値はあえて捨ててでも、顧客が本当に望んでいて自社が提供できる価値を探る」という考え方を中心に、リッツ・カールトンがルームサービスで1,000円のコカコーラを販売している、などの事例も豊富に展開しており、マーケティングの基礎を学ぶ事ができます。
2.マーケティングに必要な基礎知識
3.「バリュープロポジション」顧客が望む価値の探し方
(2)「そうだ、星を売ろう 「売れない時代」の新しいビジネスモデル」
「星を売るってなんだろう?」という気持ちで読み始めた本ですが、物が売れない飽和時代に、どんな方法で新しいビジネスモデルを考えていけば良いのかを示唆してくれる本です。
ストーリーは、長野県の阿智村で実際に起きた実話を元に、温泉旅館の新人が、自分の旅館の立て直しに挑戦する中で、地域全体を巻き込みながら活性化を実現していく内容で、ジョン・P・コッターの「企業変革の8ステップ」やジェイ・B・バーニーの「企業戦略論」など戦略論も学ぶことができます。
2.今後の地域創生に必要な考え方
3.様々な経営戦略構築のフレームワーク
マーケティング戦略コンサルタント。
1984年に慶應義塾大学工学部を卒業後、日本IBMに入社。マーケティング戦略のプロとして事業戦略策定と実施を担当。さらに人材育成責任者として人材育成戦略策定と実施を担当し、同社ソフトウェア事業の成長を支える。2013年に日本IBMを退社し独立。ウォンツアンドバリュー株式会社を設立して代表に就任。
3.「会計」をテーマとした本2冊
会計には、財務会計と管理会計という2つの領域があります。財務会計は、企業の経営状態を外部の利害関係者(ステークホルダー)に開示するために行う会計で、企業会計原則という同じ基準で財務諸表(貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書等)を作成し公表することです。管理会計は、企業内で事業別、部門別など経営者が判断を行うために必要な内部情報をまとめて事業計画書や中期経営計画などを作成することです。下記2冊では、基本的な財務会計と管理会計の仕組みを理解する事ができます。
(1)なぜ彼女が帳簿の右に売上と書いたら世界が変わったのか?
乃木坂46のアイドルが表紙とキャッチーな名前に興味を惹かれて購入した本です。乃木坂46の衛藤美彩さんが、複式簿記が存在しない架空の世界で、簿記・会計の知識を学びながら、事件を解決していく物語です。複式簿記の必要性や、「仕訳」「貸方・借方」という簿記の基礎、財務会計の基盤となる知識などを学ぶ事ができます。
2.「仕訳」「貸方・借方」という簿記の基礎
3.企業活動における財務会計の必要性
太田昭和監査法人(現・新日本有限責任監査法人)を経て、現在、澤公認会計士・税理士事務所を経営
衛藤 美彩 氏 タレント(乃木坂46の元メンバー)
(2)会計天国
BOOKOFFの会計本のコーナーで見つけて思わず購入した本ですが、ビジネスマンに必要な基礎的会計知識を学ぶ事ができます。ストーリーは、事故死した経営コンサルタントである主人公が、窮地にある5人の経営者に対して財務会計を中心に指導しながら、目指すべき経営状態へ改善をしていく内容です。会計の知識だけでなく、コンサルタントが会社を変革していくプロセスも楽しく学ぶ事ができます。
2.財務諸表の分析と取るべき改善施策
3.管理会計の基礎知識
有限会社いろは代表取締役。大企業、中小企業を問わず、販促戦略立案、新規事業、起業アドバイスを行なう経営コンサルタント
青木 寿幸 氏
公認会計士・税理士・行政書士。日本中央税理士法人代表社員・株式会社日本中央会計事務所代表取締役。
4.「組織」をテーマとした本2冊
組織論におけるビジネス書は数多くありますが、るるやま は、やはり経営学者のピーター・ドラッガーの本を読んで感銘を受けました。特に流通業の仕事で、部下のマネジメント方法に悩んでいる時に読んだ「マネジメント」は、今でもたまに読み返すバイブルとなっています。また、組織を構成する人々の活動を支援し、うまくことが運ぶよう舵取りする能力、「ファシリテーション」に関しても、るるやま は重視しており、下記の本を読んで学びました。
もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの「マネジメント」を読んだら
高校野球のマネージャーになった女性高生が、ドラッカーのマネジメントを活用しながら、野球部のマネジメントを行い、甲子園を目指すストーリですが、非常にわかりやすくて、ドラッガーの理論の基礎を学ぶ事ができます。累計270万部のベストセラーで、ドラッカーの原作も数多く引用しているので、ドラッカーの本著を読む前の入門書としておすすめの1冊です。
2.「マネジメント」の理論を身近な取り組みとして実践する方法
3.ビジネスにおける人間関係の構築方法
放送作家として数多くのテレビ番組の制作に参加。アイドルグループ「AKB48」のプロデュース等にも携わる。
その後、ゲームやウェブコンテンツの開発会社や作家を経て、現在は児童書の出版社である株式会社岩崎書店社長。
ザ・ファシリテーター1・2
「ファシリテーション」という能力は、「会議をうまく進める能力」と理解されがちですが、「組織の活性化」や「組織変革」をいう現在の企業にもっと大きな視点で必要な能力とるるやま も考えています。この2冊の本では、主人公の女性が、専門性でも年齢でも自分を上回る部下を率い、ファシリテーション能力を駆使して、全社の課題解決を実現していく物語で、組織変革を進めながら、その様々なノウハウを学ぶ事ができます。
2.ファシリテーションに必要なスキルやフレームワーク
3.ファシリテーション力を活用した組織変革の方法
マサチューセッツ工科大学(MIT)卒。工学博士(Ph.D)、経営学修士(MBA)。神戸製鋼所を経て、GE(ゼネラル・エレクトリック)に勤務。テクノロジーリーダー、マーケティング・リーダー、日本GE役員などの要職を歴任。(株)チェンジ・マネジメント・コンサルティング代表取締役
5.「生産管理」をテーマとした本2冊
るるやま は、製造業の支援を通して、「全体最適」の必要性を痛感していましたが、下記2冊の本は、その代表的な理論「TOC(Theory of Constraints:制約条件の理論」に関して学ぶ事ができる良書だと思います。また、タイトルにある通り、「企業の究極の目的(ザ・ゴール)は何か?」という本質的な問いに対する答えを、主人公である工場長の業務改善の取り組みを通して、学ぶ事ができます。
ザ・ゴール
主人公の機械メーカー工場長が、学生時代の恩師の助言をもらいながら、業務改善の取り組みを通して全体最適を実現していく物語です。TOCの概念はもちろん、問題解決に必要な目標の共有や会計数値の見方や見抜き方、業務改善の進め方等について理解ができます。
2.製造業における工場の改善の進め方
3.全体最適と部分最適
ザ・ゴール2
ザ・ゴール1では、工場長だった主人公が副社長に昇格し、グループ会社の再建に立ち向かう物語です。「思考プロセス」というサブタイトルがある通り、様々な「ツリー(現状ツリー・未来現実ツリー等)を活用して事象と因果関係を可視化し、複数人でアイディアを出しながら、解決策を導き出す問題解決方法を学ぶ事ができます。
2.TOCを応用した問題解決の思考プロセス
3.問題解決に必要なフレームワーク(ツリー)
イスラエルの物理学者。1948年生まれ。TOCの提唱者として知られる。その研究や教育を推進する研究所を設立。
(訳)三本木 亮 氏
米ブリガムヤング大学ビジネススクール卒、MBA取得。在日南アフリカ総領事館(現大使館)領事部、大和証券。
現在、国内外数社において取締役、コンサルタント。
 るるやま
るるやまビジネス小説で「経営の熱量」を感じた後は、それを具体的な成果に変えるための「知識」が必要です。
私は診断士20年目の節目に、FPと宅建という新たな武器を手に入れました。小説から学んだ「戦略」を、より強固な「人生の守り」に変えていくプロセスです。
その挑戦のきっかけとなり、合格を後押ししてくれた「実用書10選」についても以下の記事でまとめています。小説とあわせて読むことで、あなたのビジネス視点はさらに深まるはずです。
最後まで読んでいただきありがとうございます!ビジネス小説で『熱量』をチャージした後は、ぜひ「実践的な知識」も手に取ってみてください。私が半年でFP・宅建を掴み取った際に支えとなった10冊を、こちらで紹介しています。知識が繋がる感覚、最高ですよ!
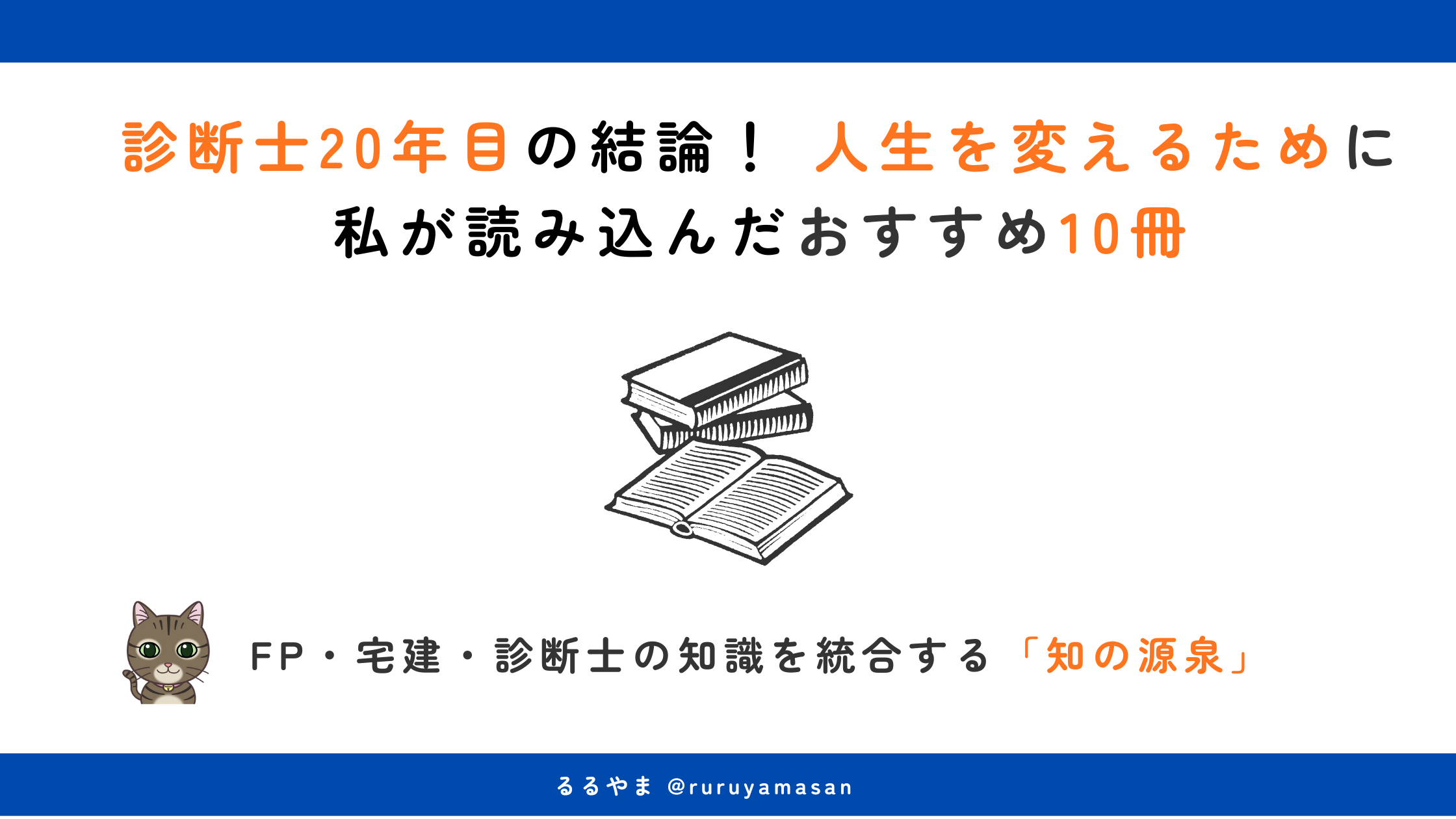
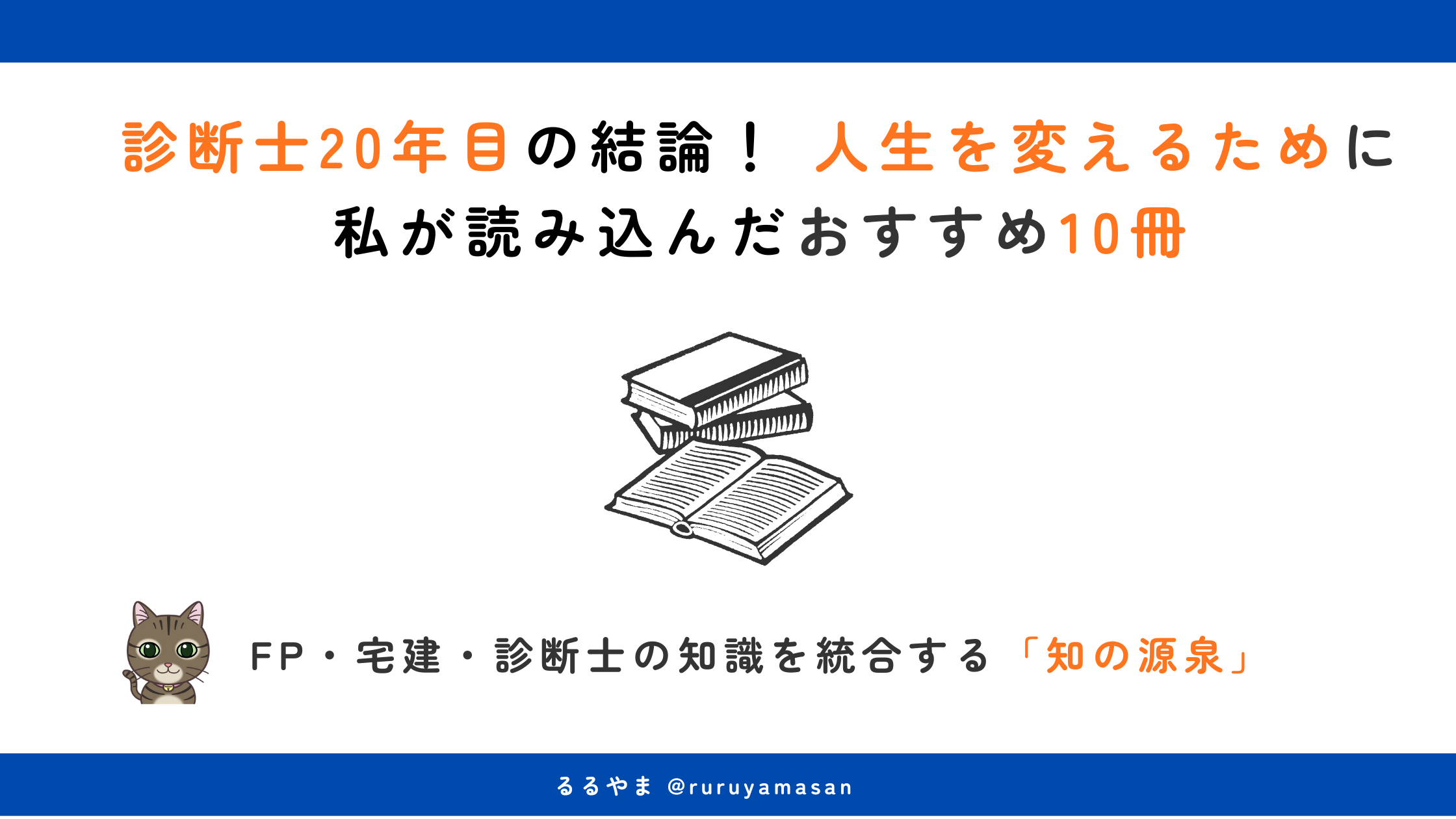
今日も、記事をお読みいただき、ありがとうございました!
るるやま @ruruyamasanでした。
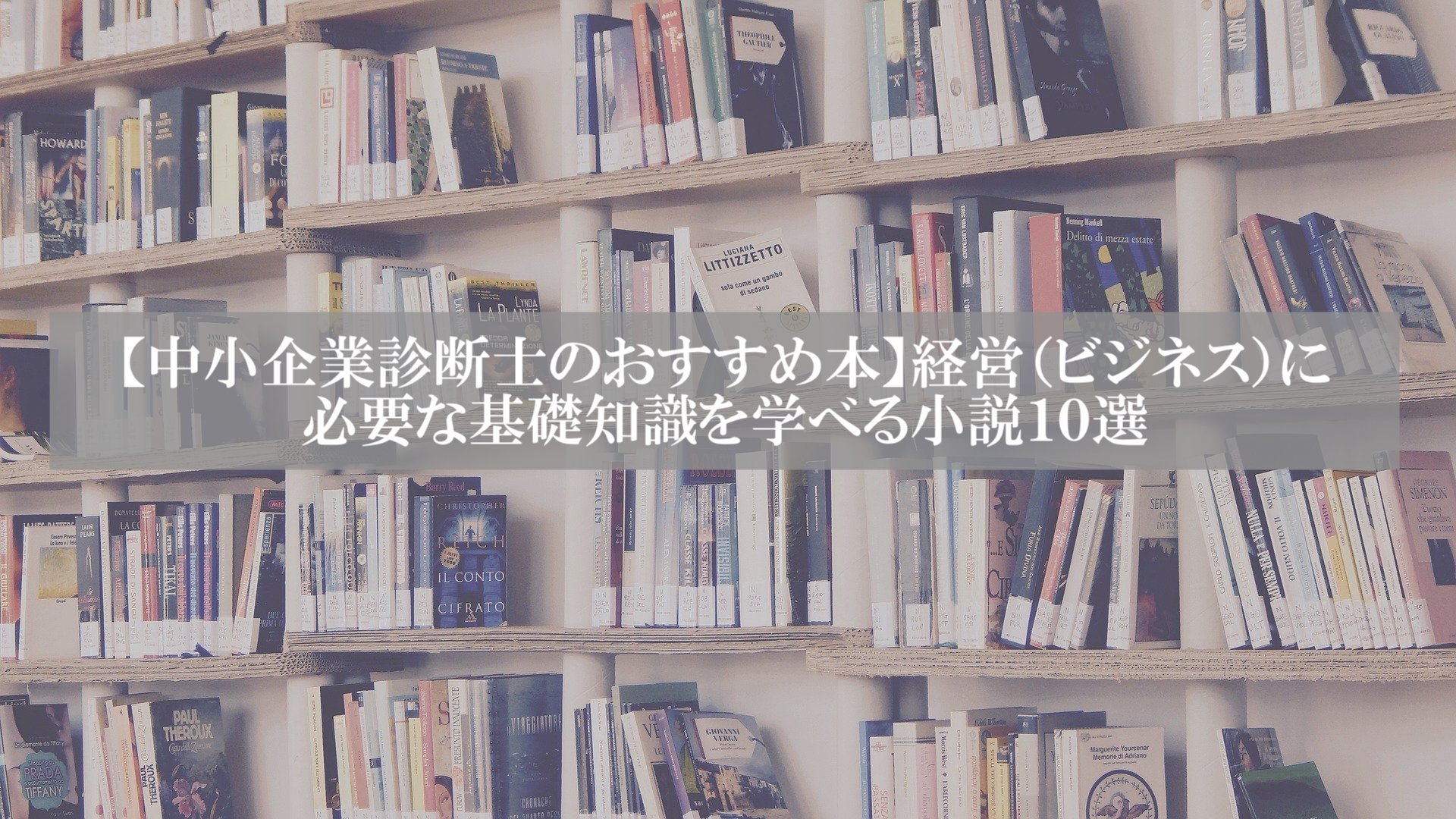


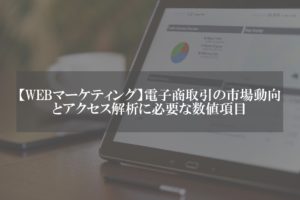



コメント