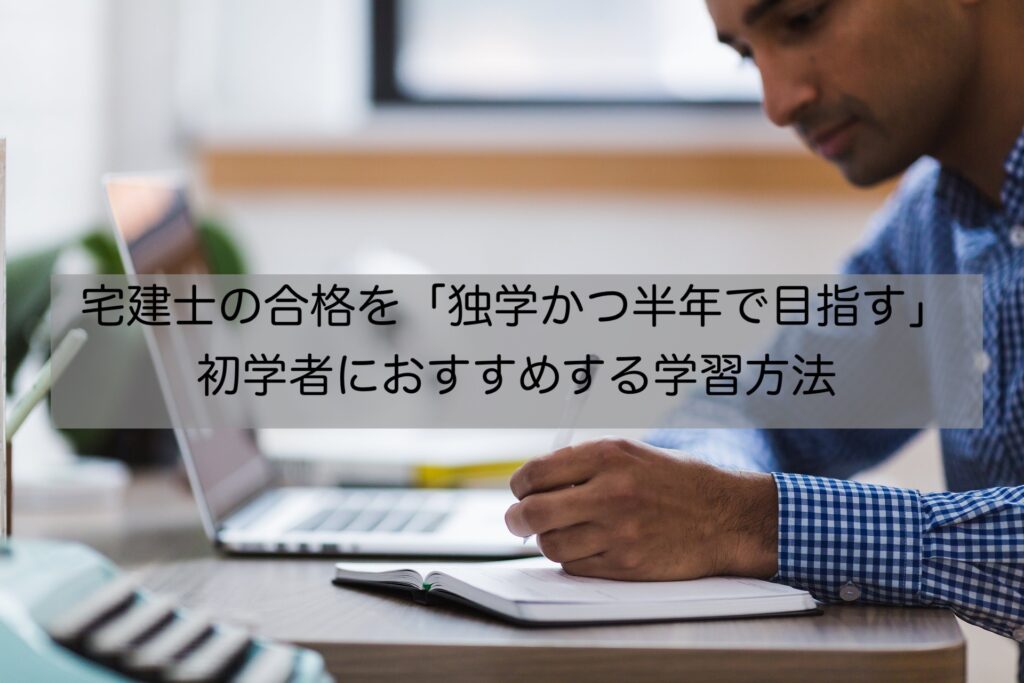
 るるやま
るるやまこんな方におすすめの記事です
1.初学者で、宅建士の勉強方法について知りたい方
2.宅建士の勉強で必要なテキストや動画について知りたい方
3.宅建士の勉強スケジュールについて知りたい方
[rtoc_mokuji title=”” title_display=”” heading=”” list_h2_type=”” list_h3_type=”” display=”” frame_design=”” animation=””]
宅地建物取引士とはどんな資格?
宅地建物取引士は、「宅建」「宅建士」と略されることの多い不動産の売買や仲介の時に必要な国家資格です。毎年約20万人が受験をしますが、合格者数は約3.8万人の17%程度で難易度は高い試験です。
宅建士は、不動産取引の専門家として、宅建士しかできない独占業務を持っており、①重要事項説明、②35条書面への署名、③37条書面への署名を行うことが可能です。
3つの独占業務の概要は、下記になります。22年5月の宅地建物取引業法の改正で、35条書面と37条書面への押印の必要は無くなりました。
①重要事項説明は、不動産取引の購入者を保護するために、売買や賃貸の不動産に関する特徴やその条件等に関して説明を行うこと。
②35条書面は、重要事項を書面にまとめたもので、説明後に宅建士自らが記名押印するもの。(宅建業法の35条に記載があることから35条書面と呼ぶ)
③37条書面は、不動産取引に関する契約書で、不動産の代金や支払い方法等を書面にまとめたもの、かつ宅建士自らが記名するもの。(宅建業法の37条に記載があることから37条書面と呼ぶ)
この3つの独占業務があるため、不動産関係の会社では、非常に価値ある実務的な資格として評価され、採用や給与面でのメリットがあります。
宅建試験の概要と学習のポイント
受験科目は、民法、宅建業法を中心に、都市計画法、建築基準法等、不動産に関する法律科目を中心とした構成になります。それぞれの科目の特徴と目標得点は下記になります。るるやまは、民法で目標点を下回りましたが、それ以外で何とか目標点を確保しました。ちなみに、22年度の合格点は、36点以上となりました。
| 科目 | 満点 | るるやま | 目標点 | 勉強方針 |
|---|---|---|---|---|
| 民法 | 14問 | 9点 | 10点 | 頻出ランクの高い項目を優先的に勉強する。 ①賃貸借・借地借家、②区分所有、③不動産登記、④相続、の4項目を優先して勉強することが重要。 |
| 宅建業法 | 20問 | 18点 | 18点 | 最も得点配分が高い科目。満点に近い点数を取る必要があるので、全ての項目を勉強することが重要 |
| 法令制限 | 8問 | 6点 | 6点 | 都市計画法や建築基準法は、頻出分野を中心にして、あまり広げすぎない勉強を行う。国土利用計画法、農地法、宅地造成等規制法、土地区画整理法は、条文が少ないため細かな条文まで押さえることが重要。 |
| 税その他 | 3問 | 2点 | 2点 | 国税や地方税といった税関連と不動産鑑定評価等に関する問題だが、その年の傾向があるので、直前期に各先生達の方針に基づいて勉強を行う。 |
| その他(5問免除) | 5問 | 5点 | 5点 | 住宅支援金融機構、景品表示法、統計、土地、建物の5分野から出題されるので、「税その他」と同様に直前期に、各先生の方針に基づいて勉強を行う。 |
| 合計 | 50問 | 40点 | 40点 |
宅建士に6か月で合格した学習法のポイントは?



るるやまは、試験に出る論点が凝縮されているテキストと過去問が単元ごとに構成された問題集、そしてテキストに連動した無料動画をフル活用して、合格することができました。
テキストの1単元を読んだ後で、その単元を見ながらYouTubeを2倍速で視聴して理解し、その上で、その単元の過去問を行う方法が、効率的でかつ定着率も高まる方法だと思います。今流行りの、タイムパフォーマンスの良い勉強方法ですね。
テキストは有料(とはいえ、3000円程度)になりますが、YouTube動画は、10分程度の無料動画のため、費用がほとんどかかりません。通勤途中の時間をうまく活用することが出来ました。
1.宅建士のインプット用おすすめテキスト
るるやまは、「宅建士出るとこ集中プログラム〈2022年版〉」を軸にインプットしました。
著者の吉野 哲慎先生は、日建学院の講師をされていて、保有資格は司法書士をはじめ、行政書士、宅地建物取引士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士、ファイナンシャル・プランナー2級等法律系の資格を中心に幅広く保有をされています。そのため、民法等の覚える量が多く、深い理解が必要な科目は、事例を交えながら、分かりやすく説明をされるので、非常にわかりやすく、スッと頭に入ってきます。他のテキストも色々見ましたが、必要最小限の重要ポイントがまとめられており、このテキストの良い点は下記3点です。
(1)宅建試験に必要な全ての科目が1冊に凝縮されていて、いつでも手元に置いて必要な項目を確認できる。
(2)1単元当たり2~3ページの構成で、ポイントが簡潔にまとまっているので、進行管理がしやすい。
(3)単元ごとに過去問から抜粋した確認問題があり、理解度を更に向上できる。
2.宅建士のアウトプット用おすすめ問題集
るるやまは、TAC出版の「みんなが欲しかった! 宅建士の問題集 2022年度」を活用しました。
1つの項目をテキストと動画でインプットした後で、その日のうちに問題集を解いてアウトプットを行うことで、定着率を高めることができました。この問題集については、5回は繰り返して解いたと思います。ただ単純に繰り返すのではなく、間違えた問題は印をつけた上で、テキストの関連する場所を復習することで、頭に残るようになりました。
この問題集の良い点は、下記3点です。
(1)分野別に頻出の過去問が掲載されているので、単元ごとに理解度の確認ができる。
(2)問題が左ページに、解説が右ページに掲載されているので、復習が効率的にできる。
(3)①宅建業法、②権利(民法)、③法令上制限、税その他、が3分冊になるので、持ち運びがしやすい。
3.宅建士のインプット用おすすめ動画
宅建士を学べる動画は、Youtubeに多くアップロードされていますが、るるやまがお勧めする動画は、3人の先生の講義です。
それぞれ、youtubeでの配信が中心のため、るるやまは「タイムパフォーマンス」の向上を意識し、「2倍速」で視聴していました。
特に、1時間の通勤時間は貴重な勉強時間となりました。
(1)宅建吉野塾
るるやまは、主要テキストの著者である吉野 哲慎 先生の動画を主に視聴していました。理解度が浅いテーマは、腹に落ちるまで、何度も繰り返し視聴しました。この吉野塾の動画を視聴するメリットは下記3点あります。
①テキストと連動した動画のため、効率的な予習と復習が可能で、理解度の向上につながる。
②一単元あたりの動画時間が、10分程度と短くコンパクトなので、細切れ時間に視聴できる。
③理解に最も時間のかかる民法の問題演習を中心とした動画もあり、宅建士だけでなく他資格問題も採用しているので、もれなく論点整理や傾向の理解ができる。



①宅建ワンコイン講座(アーガイブ配信有)
「宅建士出るとこ集中プログラム」をベースに、単元ごとの講座を10分程度でまとめて配信しています。事例を交えながら、ポイントをコンパクトに説明してくれるので、とても早く理解が進みます。2~3日ごとに新規項目が追加されていますが、4/17現在は、宅建業法の「保証協会」がアップロードされたところです。
②民法過去問研究会
毎週月曜日の9時にリアルタイム配信されて、その後1週間だけアーカイブ視聴可能な動画です。宅建士の民法分野で出題がされそうな問題を、宅建士の過去問だけでなく、司法試験や行政書士等の他資格試験も取り上げて解説を行います。問題と解説を掲載したテキストは、無料でストアーズ宅建吉野塾からダウンロードが可能ですが、当日までに行ったほうが良いです。(削除されます)
(2)宅建みやざき塾
吉野先生と同じ日建学院の講師の宮嵜 晋矢先生の動画です。非常に熱く、かつわかりやすい講義がモチベーションを向上してくれます。吉野先生の講義と合わせて聞くことで、宅建試験の傾向や重要ポイントを再度復習することができるので、おすすめです。
①宅建みやざき塾 生放送質問会
毎週水曜日9時にリアルタイム配信を行い、その後1週間程度、アーカイブ視聴が可能な動画です。毎週出題傾向の高いテーマを設定して、頻出ポイントや過去問を掲載したオリジナルレジメを元に、講義を行っています。熱心な視聴者のチャットを紹介しながら、ライブ感満載の講義になるので、頭に残る講義になります。
オリジナルレジメは、翌日には、削除されることが多いので、早めにダウンロードしておくほうが良いです。
②「サクッと3分トレ!」
今年からスタートした、毎日1本ずつ頻出テーマでアップされる動画です。こちらも合わせると更に学習効果が高くなります。
(3)「棚田行政書士の不動産大学」
棚田 健大郎 先生は、宅建士だけでなく、行政書士やマンション管理士等法律系の資格を複数持っている講師です。毎日、10分程度の動画で、頻出テーマについてわかりやすい講義をしています。吉野先生やみやざき先生の動画で学んだことを、棚田先生の動画を毎日視聴することで、更に頭への定着化が進みました。
4.宅建士のおすすめ模試
るるやまが最初に受けた模試が、7月にLECで開催される無料の模試「宅建士0円模擬試験」でした。20点台前半の点数でかなり、落ち込んだ記憶があります。夏場の7月頃から、このLECをはじめとした専門学校の模試が開始されるので、自分の強みと弱みを把握して効率的な勉強を進めるために、受けることをお勧めします。
るるやまも、合計4回の模試を受けました。オンラインでの自宅受講とリアルの会場受講の2パターンがありますが、本試験はリアル会場受験になるので、できるだけリアル会場の模試を受けたほうが良いと思います。るるやまのおすすめの模試は下記4つです。
(1)LECが行う無料の「宅建士ゼロ円模擬試験」
本試験3ヶ月前の7月中旬、LECが行う無料の模試が「宅建士ゼロ円模擬試験」です。無料といっても、他の有料模試にひけを取らない本試験レベルの難度で、解説も動画配信+テキストでしっかりとあるので、非常に有効な模試だと思います。
(2)宅建フリー模試とワンコイン模試
吉野先生が監修して行う合計3回の模試で、毎年実施されています。るるやまは、3回とも受けて、間違えたところは、吉野先生の動画とテキストで復習を行いました。また、それでも理解できないところは、解説動画のコメント欄で質問を行い、とても丁寧な回答をもらえました。
①宅建フリー模試GREEN:無料でかつyoutubeの解説動画付きの模試です。
②宅建ワンコイン模試「NABY」と「WHITE」:ワンコインの500円でかつyoutubeの解説動画付きの模試です。
(3)LECが行う宅建士模試
本試験1ヶ月前の9月中旬、LECが行う模試です。受験者数も多いですし、解説も動画配信+テキストでしっかりとあるので、非常に有効な模試だと思います。るるやまは、この試験で35点を取ることができ、前回のゼロ円模試よりも得点が伸びたので、ラストスパートへのモチベーションになりました。
(4)TACが行う直前期の宅建士全国公開模試
本試験2週間前の9月下旬から10月上旬に行う模試です。LECほどではないですが、受験者数も多く、解説も動画配信+テキストでしっかりとされています。異なる会社の模試を受けることも、効果があると思います。この試験では、32点と厳しい点数でしたが、宅建業法が19点とほぼ満点に近い点数だったので、あまり自信を落とさずに、本番を迎えることができました。



今日も、記事をお読みいただき、ありがとうございました!
るるやま @ruruyamasan でした。
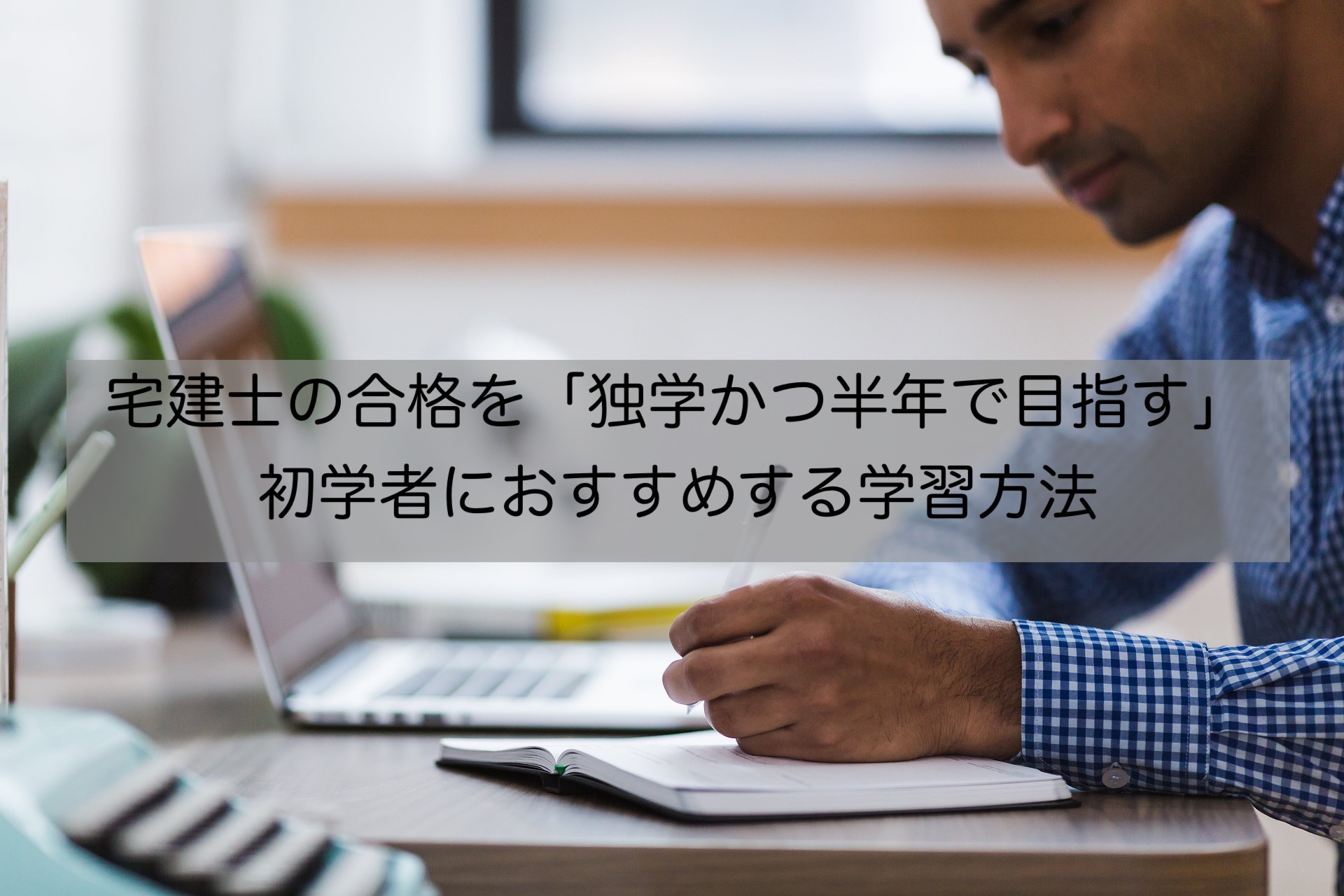
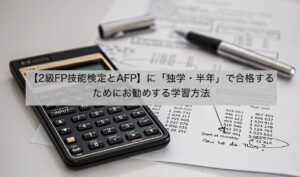
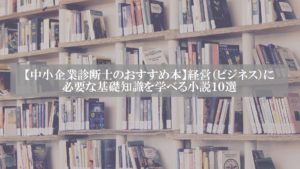


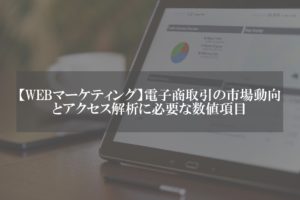



コメント